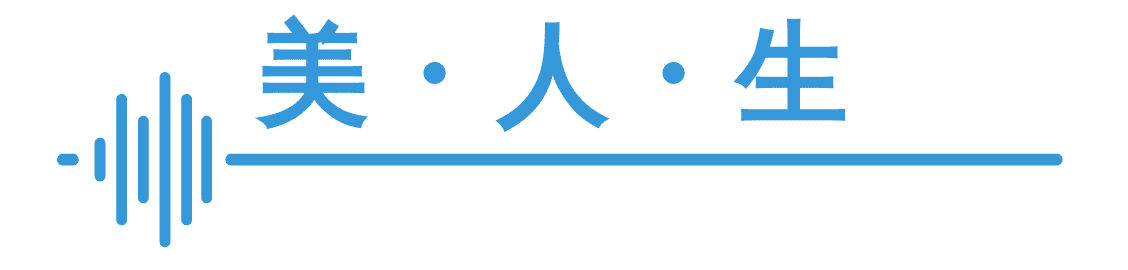ヴェネツィア・ビエンナーレ完全ガイド
ヴェネツィア・ビエンナーレは現代美術界における最高峰の国際展覧会だ。なぜなら、130年近い歴史と、各国が威信をかけて参加する国際的な規模を持つからだ。実際、1895年の創設以来、現代美術の最新動向を世界に発信し続けており、「美術のオリンピック」とも呼ばれている。この圧倒的な歴史と影響力により、ヴェネツィア・ビエンナーレは現代美術界において特別な存在であり続けている。

1. ヴェネツィア・ビエンナーレとは
1.1 基本概要
ヴェネツィア・ビエンナーレは、イタリアの水の都ヴェネツィアで開催される世界最大級の国際美術展だ。ビエンナーレとはイタリア語で「2年に一度」を意味する。美術展と建築展が交互に隔年で開催され、美術展は奇数年、建築展は偶数年に行われる形が定着している。
開催期間は例年5月から11月まで約6ヶ月間にわたる。2022年開催の第60回展では、120年以上の歴史の中でも最も多くの女性とトランスジェンダーの作家が参加し、カザフスタン、キルギスタン、ウズベキスタンなど中央アジアの国々も参加する大規模なものとなった。会期中には世界各地から7,000人以上のプレスが集まるとされ、現代美術の国際展として最も注目度が高く、影響力のある場となっている。
1.2 歴史的背景
ヴェネツィア・ビエンナーレの誕生には、都市の復興という明確な目的があった。19世紀末、イタリア統一により独立を失ったヴェネツィアは、かつての海上交易の中心地としての地位を失い、芸術分野でもミラノなどに押されていた。この状況を打開するため、1893年、ヴェネツィア市議会はウンベルト1世国王とマルゲリータ王妃の成婚25周年を記念し、「イタリア美術展」の開催を決議した。これは今で言う「街おこし」のような発想だった。
1895年4月30日、ジャルディーニ(カステッロ公園)の展示宮殿で第1回が開幕した。国王夫妻臨席のもと開催されたこの展覧会は、会期中に22万4千人の観客を集める大成功を収めた。当初から「国際展」という在り方に重きが置かれ、各国のコミッショナーが選出した作家の作品を展覧する国別参加制度と、授賞制度という特徴を持っていた。
ヴェネツィアが芸術の場として選ばれた背景には、この都市の歴史的なDNAがある。15世紀に最盛期を迎えたヴェネツィア共和国は、外交の有効なカードとして芸術を活用してきた。ジェンティーレ・ベッリーニをオスマン帝国に派遣し、ティッツィアーノのもとには神聖ローマ皇帝をはじめとする権力者たちから肖像画の依頼が殺到した。このように、芸術を通じた国際交流という伝統が、ビエンナーレ開催の土壌となった。
1.3 戦争と変革の時代
20世紀初頭、展覧会の国際化が急速に進んだ。1907年、ベルギーがジャルディーニ内に自国専用パビリオンを建設すると、各国がこれに追随した。1914年までにハンガリー、ドイツ、イギリス、フランス、ロシアが自国パビリオンを建設した。1909年の回では観客数が46万人と絶頂に達している。
第一次世界大戦で1916年と1918年の回が中止された後、ビエンナーレは近代美術や前衛芸術の紹介に焦点を当てるようになった。1920年には印象派、ポスト印象派、ブリュッケが招かれ、1922年はモディリアーニとアフリカ美術が紹介され議論を呼んだ。ただし、1910年の回では、主催者がスペイン室からピカソの絵画を「余りに目新しすぎて観客にショックを与える」として撤去し議論となった経緯もある(ピカソはこの後、1948年までヴェネツィア・ビエンナーレに展示されなかった)。
1930年代にはムッソリーニ政権下でコミッショナー制度と国際審査による授賞制度が導入され、現在の形式が確立した。しかし、第二次世界大戦により1942年から1946年まで中断を余儀なくされた。
戦後、ビエンナーレは現代美術の新しいトレンドの指標となる重要な役割を担うようになった。しかし、1968年にはパリ五月革命の影響を受けた学生たちの激しい抗議運動の対象となった。ビエンナーレが大国主義や商業主義の祭典であるとして、各国の美術関係者がボイコットを呼びかけ、美術家らが各国政府からの出展要請を断る混乱が起こった。大規模な抗議運動に対してビエンナーレ会場に警官隊が導入される事態となり、賞制度も一時廃止された。
この混迷の中、1980年に転機が訪れる。息を吹き返すべく、メイン会場のジャルディーニに加えて造船所跡のアルセナーレで若手アーティストを紹介する展示を企画した。ここでの成功が国際美術祭としての勢いを取り戻すきっかけとなり、廃止されていた賞も1986年に再開された。
1.4 21世紀の多様性と拡大
21世紀に入ると、アルセナーレが改装されて正式に二大会場制となった。各国のパビリオンの数も年々増加し、現在ではジャルディーニの園内に恒久パビリオンを所有する29カ国を含め、約90カ国がこの美術の祭典に参加している。
2000年代以降、ビエンナーレは多様性の推進においても大きな変化を遂げている。100周年を迎えた1995年には初めてイタリア人以外から総合キュレーター職が選ばれ、フランスのジャン・クレールが就任した。2022年の第59回展では、史上最も多くの女性とトランスジェンダー作家が参加し、金獅子賞に初めて黒人女性のシモーヌ・リーが選ばれるという歴史的な回となった。
2024年開催の第60回展では、アドリアーノ・ペドロサが総合キュレーターに就任した。彼はビエンナーレ史上初のラテンアメリカ出身者かつ南半球に活動拠点を置く者として、また初のクィアを公言するキュレーターとして、根強い欧米中心のモダニズムの境界や記述を問い直した。「Foreigners Everywhere(外国人はどこにでもいる)」をテーマに掲げ、世界的な注目を集めた。

2. ビエンナーレの構造と仕組み
2.1 展覧会の構成
ビエンナーレの構成は大きく三つに分かれる。第一に、全体を統括するディレクター(総合キュレーター)が企画するテーマ展がある。これは展覧会全体の方向性を示す中心的な展示だ。第二に、参加各国のコミッショナーが選抜したアーティストの展示を行う各国のパビリオンがある。第三に、そのいずれにも属さない「アペルト」のような関連企画が存在する。
この構成により、統一されたテーマと各国の独自性が共存する、多層的で豊かな展覧会が実現されている。万国博覧会や近代オリンピックのように国が出展単位となっており、国同士が威信をかけて展示を行う点が大きな特徴だ。
2.2 会場と配置
主要会場は二つある。一つ目は、ヴェネツィア市街最大の公園であるジャルディーニ(正式名はカステッロ公園)だ。当初からの会場であるジャルディーニの園内には、参加各国の政府が所有・管理する30の恒久パビリオンが建っている。恒久パビリオンを所有している国は、アメリカ、フランス、ドイツ、ロシア、南米諸国など1930年代の強国や冷戦時代の西側陣営の同盟国、その他国際社会での政治力でパビリオンを建てることのできた国である。
二つ目の主要会場はアルセナーレだ。ヴェネツィア共和国時代の国立造船所だったこの巨大な空間は、1980年から展示会場として使用され始め、2000年代以降、正式に二大会場制が確立した。
さらに、これらの主要会場以外にも、ヴェネツィア市内各所で関連展示が行われる。パビリオンを持たない国々が街中の歴史的建造物や空間を借りて展示を行うことで、街全体が巨大な美術館となる。近年では、同時期周辺部で開かれるアートフェアなどの関連イベントも爆発的に増えており、一般の鑑賞者がその全貌を把握するのは困難を極める。
2.3 賞制度
ビエンナーレの大きな特徴の一つが賞制度だ。最高賞である「金獅子賞」をはじめとする賞の行方は毎回大きな注目を集める。パビリオンやアーティスト個人を対象とする賞があり、受賞はアーティストの国際的評価を大きく高める。
ビエンナーレで展示されたアーティストは世界的な評価が高まり、作品の値打ちが上がるだけでなく、世界の様々な美術館での展示が実現することも多い。有名アーティストだけでなく、若手や知名度の低いアーティストも参加しており、世界中からアートコレクターやキュレーター、オークション関係者がこぞって集まり、新たなスターの発掘に期待を寄せている。
2.4 ビエンナーレの二つの側面
ヴェネツィア・ビエンナーレは、金獅子賞という最高賞が用意されているように展示内容を競う場であると同時に、お祭り的な側面も持っている。この二つの側面は各国のパビリオンの展示のあり方にも大きく影響している。第一の目標として掲げることはないにしても、賞を競い獲得することを大きなモチベーションとして参加しているパビリオンと、2年に一度の建築界のお祭りとしてとらえて参加しているパビリオンとが混在しているわけだ。

3. 日本とヴェネツィア・ビエンナーレ
3.1 日本の参加史
日本は1952年の第26回展より公式参加を果たした。1950年代前半、イタリア政府から日本外務省へ、ジャルディーニに空いていた最後のパビリオン用地に日本が1956年までにパビリオンを建設しない場合は他国へ用地を割り当てるという通告がなされた。日本は予算不足を理由に建設を見送るところだったが、1955年、ブリヂストンの会長だった石橋正二郎が外務省の要請に応じて資金を政府に寄付し、外務省予算と合わせて建設費が出せることになった。
吉阪隆正の設計による日本館が完成したのは1956年だった。ル・コルビュジエに師事した吉阪による日本館は、シンプルな四角い形の建築様式が特徴的だ。この年に出展した棟方志功が版画部門で国際大賞を受賞し、日本の現代美術が国際的に認められる大きな契機となった。
日本は受賞を重ねてきた歴史を持ち、現在、日本館は最も注目されている館の一つといわれている。これまでに土方定一、瀧口修造、針生一郎、東野芳明、中原佑介らがコミッショナーを務めてきた。近年では、2013年にアーティストの田中功起とキュレーターの蔵屋美香による展示が特別表彰を受賞して話題を呼んだ。
建築展については、1991年の第5回展から公式参加し、美術展と同様、毎回日本館を会場に展示を行っている。建築展も美術展と同じく、2000年以降は2年に一度の定期開催として、交互に開催する形が定着している。
3.2 最近の日本館の取り組み
2022年の第59回展では、ダムタイプが日本代表として選出された。これまでのコミッショナーのコンペティション形式は取らず、美術の専門家から構成される国際展事業委員会が選考する形が取られた。ダムタイプはビジュアル・アート、音楽、ビデオ、ダンス、デザイン、プログラミングなど様々なジャンルで制作を行うアーティストの集団で、リーダーや固定メンバーはおらず、プロジェクトごとに流動的に参加アーティストが変化していくマルチメディア・アーティスト・グループだ。本展示では、新型ウイルスの世界的流行やインターネット、ソーシャルメディアによって変わっていく人々の関係性や世界を知覚する方法について、あるいは「ポスト・トゥルース」についてのインスタレーション作品を展示した。
2024年の第60回展では、毛利悠子が日本代表作家を務めた。このように、日本は毎回現代美術の最前線で活躍するアーティストを選出し、日本館を会場に作品を紹介し続けている。

4. 2026年第61回展の最新情報
4.1 故コヨ・クオの構想を継承
2026年5月9日から11月22日まで開催される第61回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展のテーマは「In Minor Keys(マイナー調で)」に決定した。この展覧会は、2025年5月10日に急逝したキュレーターのコヨ・クオによって構想されたものであり、彼女の家族の全面的な同意と支援のもと、ヴェネツィア・ビエンナーレ財団がその構想を忠実に実現する形で実施される。
コヨ・クオは、1967年カメルーンのドゥアラで生まれたキュレーターだ。13歳までカメルーンで暮らし、その後家族とともにスイスのチューリッヒに移住し、約15年間を過ごした。経営管理と銀行業を学んだ後、アートの道に進んだ。フランス語、ドイツ語、英語、イタリア語に堪能で、1995年にセネガルのダカールを訪れたことがきっかけでアフリカ現代美術に関わるキャリアを築くことになった。
2024年10月17日、ヴェネツィア・ビエンナーレ事務局長のピエトランジェロ・ブッタフォーコから第61回展のアーティスティック・ディレクターとしての招聘を受け、同年11月5日にヴェネツィア・ビエンナーレ理事会よりディレクターへの任命を快諾した。第60回展閉幕後の12月3日の記者会見にて就任が公表された。クオはヴェネツィア・ビエンナーレ史上初のアフリカ系女性キュレーターであり、その動向には国際的な注目が集まっていた。
昨年の招聘から2025年5月初旬にかけて、クオは展覧会全体の構想から理論的な枠組みの定義、アーティストや作品の選定、展覧会のビジュアルアイデンティティや展示デザインの決定、参加を呼びかけたアーティストとの対話などを精力的に進めていた。
4.2 コヨ・クオの経歴と功績
クオは、アフリカおよびアフリカン・ディアスポラの現代美術を専門に、アートにおける脱植民地化の問題に長く取り組んできた人物だ。独立キュレーターとして活動し、2008年にセネガルのダカールにアーティストのレジデンシーと展示スペースである「ロー・マテリアル・カンパニー(RAW Material Company)」を設立した。
ドイツのドクメンタ展(2007、2012)ではキュレーター・チームの一員として名を連ね、国際的なキュレーターとしての活動以外にも、アフリカの美術や美術機関に関する著書を執筆してきた。2020年には芸術、建築、批評、展示分野での業績を称えるスイスの芸術賞・メレット・オッペンハイム賞でグランプリを受賞した。
2019年からは南アフリカ・ケープタウンにあるゼイツ現代アフリカ美術館(Zeitz MOCAA)のエグゼクティブ・ディレクター兼チーフキュレーターとして活動してきた。前任者の不祥事により揺れていた同館の改革を一手に引き受け、「When We See Us: A Century of Black Figuration in Painting」などの展覧会をキュレーションし、トレイシー・ローズやオトボン・ンカンガ、アブドゥラティ・コテナなどのアーティストの個展も企画して「美術館を生き返らせた」と評された。
2015年、ニューヨーク・タイムズは彼女を「アフリカの傑出したアート・キュレーターの1人」と評し、2014年から2022年まで、月刊誌『アート・レビュー』誌の「現代美術界で最も影響力のある100人」に毎年選出された。2020年には32位にランクインしている。
クオはキュレーターという職業を助産に例え、自分はキュレーターというよりもアーティストに「仕える者」であると認識していると語った。アーティストと時間をともにするなかで彼らの意図を汲み取り、それを「解釈・翻訳する」という考えのもと、アーティスト支援を行ってきた。
4.3 「In Minor Keys」のテーマ
「In Minor Keys」と題されたキュラトリアル・テキストは、深く息を吸い、吐いて、肩の力を抜き、目を閉じるように語りかけ、けたたましく鳴り響く騒音にかき消されそうになりながらも確かに存在する音楽、悲劇に見舞われながらも美を生み出す人々の歌、廃墟から立ち上がる人々の旋律、傷や世界を描いている。
このテーマは、クオがこれまで一貫して取り組んできたアフリカおよびアフリカン・ディアスポラの現代美術における脱植民地化の問題、周縁化された声を中心に据えるという姿勢、そして困難な状況下でも美と希望を生み出す人々の営みへの注目が凝縮されたものだ。
4.4 日本館:荒川ナッシュ医の挑戦
2026年5月から開催される第61回展において、日本館の出展作家は荒川ナッシュ医に決定した。6月14日には、荒川ナッシュを迎え、日本館のキュレーターを発表する記者会見が東京都内で開催された。日本館では初の共同キュレーターとして高橋瑞木と堀川理沙が選出された。
荒川ナッシュ医は1977年福島県いわき市出身の日系アメリカ人だ。1998年に渡米し、ニューヨークでの21年の滞在を経て、2019年にロサンゼルスへ移り、現在はロサンゼルスを拠点に活動するクィア・パフォーマンスアーティストである。ロサンゼルスのアートセンター・カレッジ・オブ・デザイン大学院アートプログラム教授を務めている。
近年では、ハウス・デア・クンスト(ミュンヘン、2025)、国立新美術館(2024)、CHAT センター・フォー・ヘリテージ・アーツ・アンド・テキスタイル(香港、2024)、東京都写真美術館(2024)、テート・モダン(ロンドン、2021)などの展覧会に参加している。様々な人物との共同作業を続け、「私」という主体を揺るがしながら、アート作品や作家の主観の不確かさをグループ・パフォーマンスとして表現している。
日本館のテーマは「草の赤ちゃん、月の赤ちゃん」だ。荒川は作家コメントで次のように述べている。
「数年前に日本国籍を喪失し、日本代表としてヴェネチア・ビエンナーレに参加する機会はないと思っていました。1966年の草間さんのゲリラ行為や1997年の内藤礼さんの空間など、ビエンナーレの歴史的なパフォーマンスと対話できるこの機会に高揚しています。パンデミック以降、日本館の選考プロセスは大きく変わりました。作家がキュレーターを選び、追加資金を調達しなければならない。国を代表するという『宿題』は複雑になってますが、見方を変えれば、今までよりさらに作家が主体性を持って展覧会に関与出来るということ。これまでの日本館でのダムタイプ、毛利悠子さんに続き、次の誰かにバトンタッチ出来るような風穴を開けたい。」
荒川は現在、夫とともにロサンゼルスのアジア系ディアスポラ・コミュニティの新しい一員である2人の子供を育てている。最近、和田夏十さん脚本の1962年の映画『私は二歳』をもう一度見たと述べ、「彼女の脚本は、2026年の日本館の私のパフォーマティブな展開のヒントとなるでしょう」とコメントしている。
会期は2026年5月9日から11月22日まで、会場はビエンナーレ会場ジャルディーニ地区内の日本館だ。主催は国際交流基金が務める。

5. ヴェネツィア・ビエンナーレの影響力
5.1 現代美術への影響
ヴェネツィア・ビエンナーレは、現代美術のトレンドを定義する場として機能している。なぜなら、世界中から最も注目されるキュレーター、アーティスト、コレクター、ディーラー、美術館関係者が一堂に会するからだ。ここで紹介される作品や議論は、その後数年間の現代美術の方向性に大きな影響を与える。例えば、2022年の第59回展で女性とトランスジェンダーの作家が大幅に増えたことは、世界的な多様性推進の流れを加速させた。このように、ビエンナーレは単なる展覧会ではなく、現代美術の未来を形作る場なのだ。
5.2 アートマーケットへの影響
ビエンナーレは、アートマーケットにも大きな影響を与える。近年では、加速する美術市場の肥大化と軌を一にするように、同時期周辺部で開かれるアートフェアなどの関連イベントが爆発的に増えている。スイスの時計メーカー〈スウォッチ〉や、イタリアを代表するコーヒーメーカー〈イリー〉といった国際的な企業がスポンサーを務めていることからも、その経済的な重要性が伝わってくる。
ここで注目された作家の作品価格は急騰し、世界的な美術館での展示機会も増える。若手作家にとっては、ビエンナーレへの参加が国際的なキャリアを築く決定的な転機となることも多い。
5.3 社会的・政治的メッセージの場
ビエンナーレは、アートを通じて社会的・政治的メッセージを発信する場でもある。楽しみを与えてくれる半面、私たちが置かれた現代社会の様々な問題、世界のどこかでこの瞬間も苦しんでいる人がいるという現状を知ることになる。アートは社会で何が起こっているかを教えてくれるだけでなく、それについて深く考えさせてくれる。
2022年の第59回展では、ウクライナ広場が注目を集め、一方でロシア館は空っぽのまま展示された。このように、ビエンナーレは世界の政治状況を映し出す鏡でもあり、アートが政治と無関係ではないことを示している。
5.4 都市と観光への影響
ビエンナーレはヴェネツィアという都市自体にも大きな影響を与えている。19世紀末に「街おこし」として始まったこの国際美術展は、今や年間数十万人の観客を集める一大イベントだ。会期中、ヴェネツィアはまさに「世界のアート首都」となり、ホテルは満室、街中がアートで溢れる。6ヶ月間の会期中、観光業から文化産業、飲食業まで、様々な産業が恩恵を受ける。
ただし、観光客の増加は「オーバーツーリズム」という問題も引き起こしている。ヴェネツィアの人口は減少を続け、地元住民の生活が観光化の波に飲み込まれつつあるという課題もある。ビエンナーレはこうした都市の矛盾も内包した存在となっている。
6. ビエンナーレの課題と批判
6.1 国別パビリオン制度への批判
ビエンナーレの国別パビリオン制度は、その成立時から議論の対象となってきた。なぜなら、この制度が国家主義を助長し、アートを国家のプロパガンダの道具にする危険性を孕んでいるからだ。1968年の学生運動では、まさにこの点が激しく批判され、ビエンナーレが「大国主義や商業主義の祭典」だとして抗議された。各国が威信をかけて参加するという構造は、アートの本来の自由な精神と矛盾する可能性がある。
さらに、パビリオンを持つ国と持たない国の格差も問題だ。ジャルディーニ内に恒久パビリオンを持つのは主に1930年代の強国や冷戦時代の西側陣営の同盟国で、多くのアフリカ諸国やアジア諸国はパビリオンを持たない。資金力のある国は市内の一等地に立派な展示空間を確保できるが、そうでない国は周辺部での展示を余儀なくされる。この構造は、旧来の植民地主義的な権力構造を反映しているとの批判もある。
6.2 商業主義との共存
ビエンナーレが大規模化し、国際的な注目度が高まるにつれ、商業主義との距離が問題視されるようになった。会期中にはアートフェアが乱立し、コレクターやディーラーがこぞって集まる。展示される作品の多くは販売を前提としており、アートが商品化される側面は否定できない。
スポンサーシップの問題もある。国際的企業がスポンサーとなることで、展覧会の独立性や批評性が損なわれる可能性が指摘されている。アートが企業のマーケティングツールとなってしまう危険性だ。ただし、スポンサーなしでこれほど大規模な国際展を維持することも困難であり、理想と現実のバランスが常に問われている。
6.3 環境への配慮
近年、大規模な国際展覧会の環境負荷が問題視されるようになっている。世界中から数十万人の観客が飛行機でヴェネツィアに集まり、大量の展示物が世界各地から輸送される。展示のために大量の資材が使われ、会期終了後には多くが廃棄される。カーボンフットプリントの観点から、こうした大規模イベントの持続可能性が疑問視されている。
ヴェネツィア自体が気候変動による水位上昇で危機に瀕している都市であることを考えると、この問題はより切実だ。ビエンナーレ運営側も環境への配慮を強化しているが、根本的な解決には至っていない。
6.4 多様性と包摂性の課題
近年、ビエンナーレは多様性の推進に力を入れているが、まだ課題も多い。2022年に史上最も多くの女性とトランスジェンダー作家が参加したことは画期的だったが、それでも男性作家が多数を占める状況に変わりはない。西欧中心主義の脱却も叫ばれているが、実際には欧米のアート市場の論理が支配的だ。
言語の問題もある。展覧会の説明は主に英語、イタリア語で書かれており、他の言語話者にとってはアクセスしにくい。アートワールドの共通言語が英語であることは、非英語圏のアーティストやキュレーターに不利に働く可能性がある。

7. ビエンナーレの未来
7.1 デジタル化とオンライン展開
新型コロナウイルスの世界的流行は、ビエンナーレのあり方にも影響を与えた。物理的に会場を訪れることが困難になった時期、オンライン展示やバーチャルツアーの重要性が認識された。今後、デジタル技術を活用した展示形態がさらに発展する可能性がある。
ただし、ヴェネツィアという特別な場所で、実際に作品と対峙する体験の価値は変わらない。デジタルはあくまで補完的な役割を果たすものであり、リアルな体験を代替するものではないだろう。むしろ、デジタルとリアルのハイブリッドな展示形態が模索されていくと考えられる。
7.2 持続可能性への取り組み
環境問題への意識の高まりを受けて、ビエンナーレは持続可能性をより重視していく必要がある。輸送方法の見直し、再利用可能な展示資材の使用、会場でのエネルギー効率の改善など、具体的な対策が求められている。
また、テーマ設定においても、気候変動や環境危機を扱う展示が増えていくだろう。アートが環境問題への意識を高め、行動変容を促す役割を果たすことが期待されている。
7.3 グローバル・サウスの台頭
2024年に初のラテンアメリカ出身者かつ南半球に活動拠点を置くアドリアーノ・ペドロサが総合キュレーターに就任し、2026年には初のアフリカ系女性キュレーターであるコヨ・クオの構想が実現される。これは、従来の欧米中心主義からの脱却を示す重要な転換点だ。
今後、グローバル・サウスのアーティストやキュレーターの存在感がさらに増していくだろう。アフリカ、ラテンアメリカ、アジアの視点が、現代美術の議論において中心的な位置を占めるようになることが予想される。ビエンナーレは、こうした世界的なパワーバランスの変化を反映し、より多元的な場となっていくはずだ。
7.4 テクノロジーとアートの融合
AI、VR、AR、バイオアートなど、新しいテクノロジーを用いたアート作品が増えている。ビエンナーレは常に最先端の表現を紹介する場であり、今後もこうした実験的な作品が数多く展示されるだろう。
テクノロジーは単なる表現手段ではなく、私たちの存在や社会のあり方を問い直す道具となる。AIが生成した作品の作者性は誰にあるのか、バーチャル空間での体験は「リアル」なのか。こうした根源的な問いを、ビエンナーレは提示し続けるだろう。
7.5 社会とアートの関係性の再定義
ビエンナーレは、アートが社会においてどのような役割を果たすべきかという問いを常に投げかけてきた。1968年の抗議運動以来、アートの自律性と社会的責任のバランスが議論され続けている。
今日、気候変動、格差、戦争、難民問題など、人類が直面する課題は山積している。こうした状況下で、アートは何ができるのか。単なる美的体験を提供するだけでなく、社会変革の触媒となることが求められている。2026年のテーマ「In Minor Keys」が示唆するように、小さな声、周縁化された声に耳を傾け、支配的な物語に対抗する物語を紡ぐこと。これがビエンナーレの、そして現代アートの重要な役割となっていくだろう。

8. ビエンナーレを訪れるために
8.1 会期と開館時間
美術展は例年5月から11月まで約6ヶ月間開催される。2026年の第61回展は5月9日から11月22日まで開かれる予定だ。会期が長いため、ゆっくりと計画を立てて訪問できる。
開幕直後の数週間は専門家向けのプレビュー期間となり、世界中からアート関係者が集まるため非常に混雑する。一般観客にとっては、6月以降の平日が比較的ゆったりと鑑賞できる時期だ。
8.2 チケットと入場
チケットは事前にオンラインで購入することが推奨される。会場は主にジャルディーニとアルセナーレの二つで、両方にアクセスできる共通チケットが販売される。各国パビリオンは入場無料だが、メインの展示を見るにはチケットが必要だ。
学生割引やグループ割引もあるので、条件に合う場合は活用したい。また、ヴェネツィア市民向けの特別料金も設定されている。
8.3 見学の計画
全てを1日で見ることは不可能だ。少なくとも2〜3日は確保したい。ジャルディーニとアルセナーレだけでも半日以上かかり、市内各所の展示を含めると1週間でも足りないほどだ。
事前に関心のあるパビリオンや作家をリストアップしておくと効率的だ。公式ウェブサイトやアプリで展示マップと情報を確認できる。音声ガイドのレンタルもあり、理解を深めるのに役立つ。
歩き回ることになるので、快適な靴を履いていくことが重要だ。ヴェネツィアは石畳の道が多く、橋の上り下りも頻繁にある。夏は暑く、日差しも強いので、帽子や日焼け止めも忘れずに。
8.4 宿泊と移動
ヴェネツィアの宿泊費は高額なので、予算に合わせて近郊の街に泊まるという選択肢もある。メストレやパドヴァなどから電車で通うことも可能だ。ただし、ビエンナーレ期間中は観光客が多く、早めの予約が必須だ。
ヴェネツィア市内の移動は徒歩か水上バス(ヴァポレット)が基本だ。ヴァポレットの1日券や数日券を購入すると便利だ。タクシーボートもあるが料金は高い。
8.5 関連イベント
ビエンナーレ期間中、市内各所でトークイベント、パフォーマンス、映画上映、パーティーなど様々な関連イベントが開催される。アーティストやキュレーターとの対話の機会もあり、より深い理解が得られる。
ただし、こうしたイベントの多くは専門家向けで、招待制のものも多い。公開イベントの情報は公式サイトや現地で配布されるフライヤーで確認できる。
9. ビエンナーレの鑑賞のポイント
9.1 予備知識なしでも楽しめる
現代アートに詳しくなくても、ビエンナーレは十分に楽しめる。作品の前に立ち、自分がどう感じるか、何を考えるかが最も重要だ。専門知識がないことを恥じる必要はない。むしろ、先入観なしに作品と向き合えることは強みとも言える。
ただし、作品の背景や作家の意図を知ることで、より深い理解が得られることも確かだ。展示室の壁に掲示された説明文や、音声ガイド、カタログなどを活用すると良い。
9.2 多様な視点を持つ
ビエンナーレでは、世界中から集まった様々な文化的背景を持つアーティストの作品を見ることができる。自分とは異なる視点、価値観、経験に触れることが、この展覧会の醍醐味だ。
作品を「理解できない」と感じることもあるだろう。それは自然なことだ。重要なのは、なぜ理解できないのか、何が自分と作家の間に隔たりを生んでいるのかを考えることだ。そこから新しい発見が生まれる。
9.3 時間をかけて味わう
現代アートの中には、一瞬で理解できるものもあれば、長時間向き合うことで初めて何かが見えてくるものもある。映像作品であれば、最初から最後まで見る時間を取りたい。インスタレーション作品であれば、空間の中を歩き回り、様々な角度から体験したい。
疲れたら休憩を取ることも大切だ。会場にはカフェやベンチがあり、作品について考えを巡らせる時間を持てる。
9.4 対話を楽しむ
ビエンナーレは対話の場でもある。一緒に訪れた人と感想を語り合うのも良いし、現地で出会った人と意見を交わすのも楽しい。SNSで感想をシェアしたり、他の人の投稿を見たりすることで、自分とは異なる視点に気づくこともある。
公式のトークイベントやワークショップに参加できれば、より専門的な議論に触れられる。アーティストやキュレーターの言葉を直接聞ける機会は貴重だ。
9.5 記録を残す
写真撮影が許可されている作品は多いので、記録を残すと良い。ただし、一部の作品は撮影禁止なので、標識に注意する必要がある。また、他の観客の鑑賞を妨げないよう配慮も忘れずに。
メモを取るのもおすすめだ。印象に残った作品、考えたこと、疑問に思ったことを書き留めておくと、後で振り返る際に役立つ。

10. 結び:ビエンナーレの意義
ヴェネツィア・ビエンナーレは、単なる美術展覧会を超えた存在だ。なぜなら、それは現代美術の最前線を示すと同時に、私たちの社会が直面する課題を映し出す鏡であり、異なる文化や価値観が出会い対話する場だからだ。130年近い歴史の中で、戦争や社会変動を経験し、批判にさらされながらも、常に時代と向き合い続けてきた。
2026年に開催される第61回展は、コヨ・クオという卓越したキュレーターの遺志を継ぐ形で実現される。「In Minor Keys」というテーマは、支配的な声ではなく、小さな声、周縁化された声に耳を傾けることの重要性を訴えかける。それは、アフリカ現代美術の脱植民地化に取り組んできたクオのキャリア全体が凝縮されたメッセージだ。
ビエンナーレが提示するのは、完成された答えではない。むしろ、問いかけだ。アートとは何か、美とは何か、私たちはどう生きるべきか。作品の前に立つ私たち一人ひとりが、これらの問いに向き合い、自分なりの答えを見つけていく。その過程こそが、ビエンナーレの真の価値なのだ。
グローバル化が進み、デジタル技術が発達した現代においても、ヴェネツィアという物理的な空間に世界中から人々が集まる意義は失われていない。水の都の石畳を歩き、歴史的な建造物の中で最新のアート作品と対峙し、様々な背景を持つ人々と出会う。その体験は、オンラインでは決して代替できない豊かさを持っている。
ビエンナーレは、私たちに世界の広さと多様性を教えてくれる。同時に、人間という存在の普遍性も示してくれる。文化や言語が違っても、人々は美を求め、表現し、対話する。困難な状況下でも、創造性は失われない。「マイナー調」の中にこそ、深い美と真実がある。
これからもヴェネツィア・ビエンナーレは、現代美術の最前線であり続けるだろう。同時に、その課題にも向き合い続ける必要がある。国家主義、商業主義、環境問題、格差。これらの問題を克服し、より包摂的で持続可能な形へと進化していくことが求められている。
2026年、ヴェネツィアで世界中のアーティストとキュレーターが集い、新しい対話が始まる。コヨ・クオの遺志を継いだ展覧会が、どのような問いを投げかけ、どのような対話を生み出すのか。今から楽しみでならない。そして、その場に立ち会える幸運を持つすべての人々に、開かれた心と好奇心を持って作品と向き合うことを勧めたい。
ビエンナーレは、アートの祭典であると同時に、人間性の祝福でもある。困難な時代だからこそ、美と創造性の力を信じ、多様な声に耳を傾け、対話を続けることの意義は大きい。ヴェネツィアで生まれる出会いと発見が、私たちの視野を広げ、世界をより豊かに理解する助けとなることを願っている。